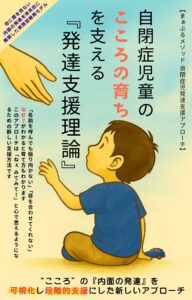【ASD発達段階アプローチ】
ASD発達段階アプローチは、ASD児が直面しやすい発達上のつまずきを「心の発達段階」を基盤に整理し、共同注意・意図理解・社会的参照など内面の発達を段階的に支援する先駆的な療育手法です。
1. 特徴
2.発達フェーズの構造
3.よくある発達のつまづきと対応ステップ例
ASD(自閉スペクトラム症)では「人への関心の薄さ」や「相手の気持ちがわからない」「空気が読めない」など他者とのコミュニケーションに著しい障害があることが特徴の一つです。「ASD発達段階アプローチ」は「ヒトとの関係の成長」を中心に置いています
1.特徴
・支援を“特性別”ではなく“発達段階別”に整理
・だれにでもわかりやすい「可視化モデル」
・支援者・保護者が共通理解できる段階構造
成長の発達段階を、「ヒトの認知 」→ 「期待感の育成」→ 「気持ちの共有」 → 「安心」 → 「共感 」という流れで捉え、16のステップに細分化して可視化。子どもの「今どこにいるか」を支援者全員で共有しながら、次のステップへと導く方法です。
2.発達フェーズの構造
| フェーズ | 主なテーマ | 支援目標 | ステップ |
| フェーズ1 | ヒトの認知 | ヒトとモノの違いに気づく、注視する | ステップ1~3 |
| フェーズ2 | 期待感の育成 | 繰り返し遊び→変化→関係性(二項関係)の形成 | ステップ4~7 |
| フェーズ3 | 三項関係と共感 | モノの共有、感情の共有、心理的安全基地 | ステップ8~16 |
| フェーズ4 | 集団との関係性 | 社会性や夜叉配慮、仲間とのつながり |
この構造は「内面の発達段階を可視化した療育モデル」として他に類を見ないユニークな実践型支援法です。
フェーズ1から3ではさらにステップ1〜16に分かれており、子どもの発達に合わせた支援内容が明確に設計されています。
・ASD児が超えられない3つの発達の壁とは?
・ASD児の成長と「ヒト>モノ」構造の歪み
・16ステップのこころ(内面)の発達到達イメージとは
3.よくある発達のつまづきと対応ステップ例
・「人の顔を見ない」
まだ「人」に注目する準備が整っていない段階かもしれません。モノとの関係に強く引かれている場合があります、人を気にする想いがなく視線を交わす必要性を感じていない状態です。ステップ1〜3を意識した支援が必要です。
・「人と“一緒に”遊べない」
人とは関われてもまだ物に対する興味が上回っている段階。一人遊びが好きで、人に関わらなくても完結できてしまっている状態です。「人と遊ぶともっと楽しい!」という経験を積むためにステップ4〜6の支援が必要です。
・「貸し借りがまだできない」
キーパーソンによる貸し借りがまだできない場合、自分の物としての意識が強く、他者の気持ちの共有ができていません。物を使った遊びを通して「期待感を共有する」遊びをたくさん経験するステップ8〜10の支援が必要です。
【事例紹介・実践事例】
1.支援者からの声(実践事例)
2.保護者の声
まぁぶるメソッドは、子どもの内面の発達段階に合わせて支援を行うアプローチです。
“この子の今“に合わせた関わりだからこそ、小さな「できた」「わかった」「笑った」が日々生まれています。
ここでは、そんな“成長の兆し”を見守ってきた支援者や保護者の声をご紹介します。
1.支援者からの声(実践事例)
実践事例①:「目を合わせてくれるようになった日」
もちろん、目を合わせるのも避けられていました。
最初は “人”として意識されていないような感覚でした。
それが今では、私が部屋に入るとすぐに探すような視線を感じるんです。
見つけると、じーっと私を目で追いかけてきます。
しかも、目が合ってもしばらくそらさないで、私の動きを見て笑うんです。気づくと、向こうからすっと近づいてきて…。
その一連の流れに「私を認識してくれたんだ」と関係性ができたことに嬉しくなりました。
(まぁぶるキッズ・保育士M:ステップ3実践中)
実践事例②:「初めて“抱っこ”をせがんできた日」
活動の最後にいつものように「おしまいにしようか」と声をかけて座ったところ、
その子がふらっと近寄ってきて、私の足にぴたっとくっついてきたんです。
そして、少し間を置いてから、無言で腕を上げて“抱っこ”のサインをしました。
驚きと同時に、今まで築いてきた関係性が実を結んだ気がして、胸がいっぱいになりました。
この瞬間を見逃さず、しっかり受け止められたことが何より嬉しかったです。
(まぁぶるキッズ・児童指導員S:ステップ6実践中)
実践事例③:「ヒトとの関係を“見る目”が育ってきた」
遊びに夢中になっているように見えても、それが“モノ”に向いているのか、
“ヒト”と一緒に楽しんでいるのか、判断がつかないことが多くて。
でも、最近は違うんです。
同じ遊びでも「この子は“ヒト”との関係性で楽しんでいるな」とか、
「あ、今は“モノ”だけで遊んでるんだな」と分かるようになってきました。
子どもと関わる中で、“見えるようになる視点”が自分の中に育ってきたことが嬉しくて。
子供の内面を見て、関係の“芽生え”を見逃さない視点、大切にしていきたいです。
(まぁぶる・支援スタッフT:ステップ2〜3実践中)
2.保護者の声(抜粋)
👩保護者Aさん(4歳男児)
自分から行きたいなんて、保育所でもどこでもそんなことはなかった。先生たちと楽しいやりとりを重ねてきたおかげだと思います。
👨 保護者Bさん(5歳女児)
家でも「いっしょにやろう!」と笑顔で誘ってくれるようになったんです。
まぁぶるでしか受けられない療育が本になりました
自閉症児童のこころの育ちを支えるASD発達段階アプローチの理論を『発達支援理論』として書籍になりました
詳しくはこちらへ